企業情報
関東大震災が発生した大正12 年(1923年)4月に初代石井喜八郎は、紙製品加工やきもの包装紙の加工等を手掛ける「石井文庫紙店」として、日本橋堀留町に創業しました。
2 代目石井喜太郎は、昭和36 年(1961 年)に株式会社石井文庫に改組、包装掛紙(のし紙)や挨拶状等の受注印刷を開始しました。現在代表を務める石井啓一は、平成6 年(1994 年)、時代ニーズに適応するためのイノベーションとして、ソフトウェアの自社開発・販売メーカーへの事業転換をし、平成9 年(1997 年)に日本の贈答文化をデジタルで再現するソフト「筆の達人®」を開発しました。
以降、12世代にわたるバージョンアップ(V1 ~ V11、Web Next)や、新たなサービス「外字の達人」、「絆の達人」、「宛名自動レイアウトの達人」、「ギフトの達人」などの「製品ラインナップに対するWebサービス化」開発を行い、併せてAI機能を含めたサービスの提供を開始し現在に至っております。

オフセット印刷機を
導入
(昭和36年)

筆の達人®Ver.4
(平成13年)

外字異体字鑑書体を
株式会社富士通と
共同開発
(平成16 年)
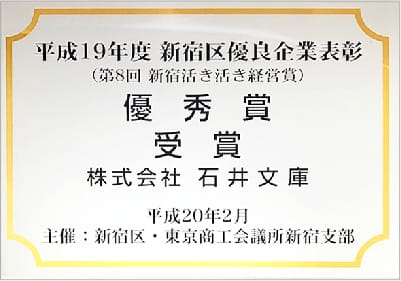
新宿区優良企業賞
優秀賞受賞
(平成20年)

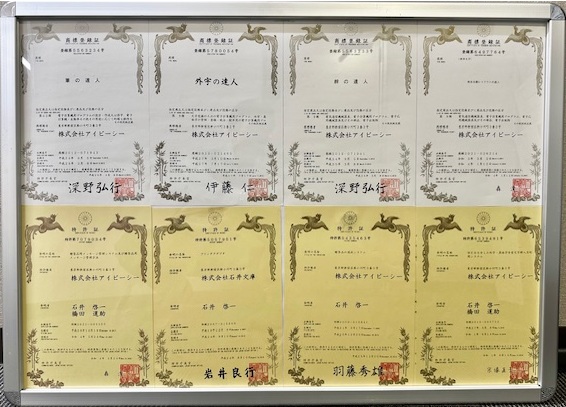
特許・登録商標1
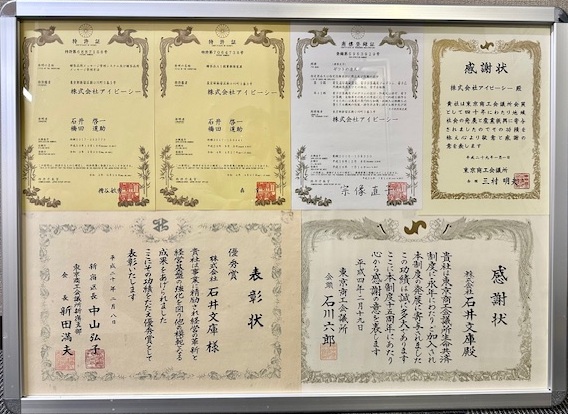
特許・登録商標2

日本の包装文化と文庫
「文庫」と聞くと、「文庫本」や書物がたくさん保管されている「蔵」、そして「図書館」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、包装文化にも関わりがあります。
古来より手回り品を和紙や風呂敷に包み、大切に保管していた箱が「文庫(文庫箱)」です。
室町時代頃からは装飾を施して“飾り物”としても用いられており、今では手頃な価格のものから高価な伝統工芸品まで様々な装飾を施した「文庫」が、大切な品物を保管するために販売されています。
また、室町時代より反物(きもの)を包む際の紙を「文庫紙(多当紙)」と呼んでいました。文庫紙は和紙でできており、通気性や吸湿性に優れています。更に和紙にはハリ感があり、着物にシワがつくのを防いでくれることから、大切な着物を包むのに適していました。
このように、大切な品物を包装する物に対して「文庫」という言葉が使われてきました。
アイビーシーと文庫
株式会社アイビーシーの歴史は、大正12 年に文庫紙(多当紙)等の加工販売を行う「石井文庫紙店」として始まり、昭和に入り印刷加工業に従事しました。
現在はICT分野において「のし紙・掛紙・カード」等の文字や画像印刷ソフト開発を主に、写真・画像、音声・動画等多次元においてメッセージを贈れる技術により、ギフトの価値を高めるサービスの開発および販売にも注力しております。
日本の包装文化である「文庫」への思いは、最新テクノロジーを活用した現在の自社製品に受け継がれ、次世代の新たな需要へのご提案となっております。